芥川龍之介のおすすめ短編10選
日本文学の巨匠、芥川龍之介は、その独特な視点と深い心理描写で多くの読者を魅了してきました。彼の短編小説は、短いながらも豊かな内容を持ち、読む者に強い印象を残します。
今回は、芥川の作品の中から特におすすめの短編10選をご紹介します。彼の作品を通じて、時代を超えた人間の本質や社会の矛盾に触れ、心に響く物語の世界をお楽しみください。
羅生門
-e1749420391272.jpg)
平安時代、天変地異や飢饉のせいで都は荒廃しきっていました。平安京の朱雀大路の羅生門で、貴族から解雇された下人が途方に暮れています。お金もなく、仕事にもありつけず、盗賊になるしかないのではと思っていますが、勇気が出ません。
門の2階に行くと、数多くの遺体が打ち捨てられている中で、1人の老婆を見かけます。彼女は、身寄りのない遺体から髪の毛を抜いてかつらを作って売ろうとしているとのこと。下人は正義感から彼女に斬りかかりましたが、老婆は「生きるためには仕方がない。死んでいった人間も恨まないだろう」と居直ります。この言葉に下人も泥棒になる覚悟ができ、居直って老婆の着物を強奪します。「自分もそうしなければ、生きていられないからな」と言い残して。この小説では、限界まで追い詰められると、人間というものはとことん利己的になるということを表現しているかのようですね。(引用元:ブックランチ)
.jpg)
語り手は、精神病で入院している「第二十三号」と呼ばれる患者。第二十三号が3年前に登山している際に、河童を見かけ後を追い、河童の国に迷い込んでしまいます。
河童の世界に飽きた語り手は、だんだん若返った姿になっていく高齢の河童から、人間の世界への帰り道を教わります。
もう二度と来られないと念を押されても、元の世界に戻ります。年を取った河童が心配したとおり、語り手は「河童が人間よりもより高潔な存在だ」と考えて河童の国を懐かしく感じ、戻りたいと思うようになるのです。
『河童』は当時の日本社会を批判した小説で、芥川龍之介の自殺する原因の1つではないかともいわれています。
(引用元:ブックランチ)
蜘蛛の糸
地獄変
.jpg)
絵仏師の良秀は、天下一品の腕前と評判でした。堀川の大殿に寵愛を受けた美しく優しい性格の娘がいましたが、彼女は大殿になびかず、良秀も娘を家に戻してほしいと願い出ています。
ある時、堀川の大殿は地獄変の屏風絵を良秀に依頼しました。
良秀は、燃え盛る牛車の中で苦しむ女房の絵がうまく描けないことに悩みます。堀川の大殿は良秀親子に企むところがあり、その情景の再現を約束するのです。地獄変は『宇治拾遺物語』の「絵仏師良秀」を下敷きにしています。「芸術のためには家族を犠牲にしてもかまわない男の話」ですが、芥川龍之介が描く良秀はどうなのでしょうか。
(引用元:ブックランチ)
鼻
.jpg)
京都の高僧「禅智内供(ぜんちのないぐ)」は、自分の長く大きな醜い鼻をしていました。陰で人に笑われ、あえて平然と振る舞ってはいましたが、ひどく傷ついていたのです。
ある日、医者に鼻を短くするやり方を聞き、念願かなって人並みの鼻になります。
これで笑われなくなる…と喜ぶ禅智内供。しかし、表向きは全然気にしていないふりして、本当は違かったのかと、余計に笑い者になるのです。
『鼻』は夏目漱石から、人の心の描き方を絶賛された小説。
(引用元:ブックランチ)
トロッコ

工事現場の近くに住む良平という少年は、作業現場のトロッコが気になって仕方なくなりました。
建設現場の工員に頼んで、一緒に動かしてもらえることになります。
とても喜びましたが、家から離れるにつれて不安になります。
工員から自分たちは現場に宿泊できるが、お前は家に1人で帰らなければならないと告げられます。
不安が的中し、日が暮れて暗くなるなか一生懸命家に向かって走り、やっとの思いで家に入るのです。
大人になった良平は仕事に疲れると、ひとりでに当時険しい道を辿ったことを思い出します。
(引用元:ブックランチ)
藪の中
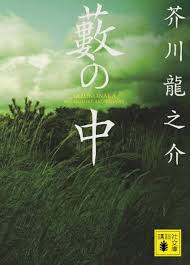
舞台は平安時代、藪の中でみつかった侍の遺体。捜査にあたった検非違使は、第一発見者の木こりの男、事件の前日に侍と馬に乗った女を見た旅の法師に話を聞きます。
また、部下の放免にも、男の衣服を身にまとった強盗の多襄丸を捕えた経緯を尋ねます。
『藪の中』は、推理小説のように事件の解決を目的としたものではありません。
どのような意図でこの小説を書いたのかは分からず、今後の研究に委ねられているようです。有識者の間では外から見た印象と、本当のことは違うことがあるということを書きたかったのではという説が有力です。この小説により、関係者の証言が食い違いがあり真相が分からないという意味で「藪の中」という言葉が使われるようになりました。(引用元:ブックランチ)
蜜柑

主人公の「私」は、自分の退屈な人生に疲れを感じていました。
電車の出発直前に、田舎じみた女の子が慌てて乗車して、目の前に座ります。
ただでさえ疲れているのに、私はますます不愉快な気分になるのです。女の子は鉄道の蒸気が入ってくるのにも関わらず、むりやり窓を開けてしまいました。もくもくと灰色の煙が入ってくるのにも気にせず、手にしていた風呂敷から鮮やかな色の蜜柑を投げます。
踏切の辺りで、小さな子どもたちの歓声が聞こえてきます。奉公に出なくてはいけない女の子が、小さな兄弟に別れの品を投げたようです。私はすっかり気分が良くなりました。
灰色の無彩色の煙と鮮やかな蜜柑の色の対比が見事。(引用元:ブックランチ)
杜子春
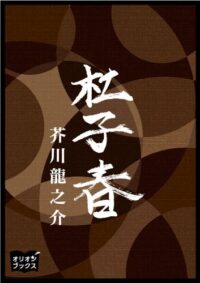
金持ちの息子だった杜子春は、親の遺産を遊びに使い、一文無しの状態になっていました。
門の側であった老人がと思春を憐れんで、この場所を掘るようにというと、荷車がいっぱいになるくらいの金品が出てきます。
3年後も再び同じようなことが繰り返され、また3度めもすっかり財産をなくしてしまいました。
杜子春は老人に話します。
お金がある時は周囲もちやほやするが、なくなるとすぐに離れていってしまう、と。
老人を仙人だと見破った杜子春は、自分も仙人になりたいので修行をさせてほしいと頼み、老人は快諾しますが…。
(引用元:ブックランチ)
芋粥
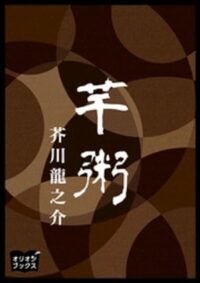
平安時代の五位(身分の低い役人)はうだつの上がらない男です。
同僚や道端にいる子供たちにも馬鹿にされる始末ですが、そんな彼の夢は腹いっぱい芋粥を食べること。
ふと望みをつぶやいたところ、裕福な藤原利仁からの招待を受けて彼の敦賀の領地まで出向きます。
しかし、大鍋いっぱいに出された芋粥を見て、彼の食欲は失せてしまうのです。
藤原利仁は大勢の前で、五位の役人の夢をあざ笑うように無理に招待します。
嫌味であるかのように大きな器に用意し、かえって食欲を失わせるのは、「芋粥を腹いっぱい食べる」という夢を無理に奪ってしまう行為にも見えますね。
(引用元:ブックランチ)
まとめ
芥川龍之介のおすすめ短編10選,いかがでしたか?
昭和の文豪!芥川龍之介の作品は独特な視点や深い洞察力を感じることができるものばかりです。
ぜひ読んでみてください。

.jpg)


コメント